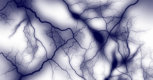脊髄小脳変性症の特徴
常染色体劣性遺伝性脊髄小脳変性症は小児期に発症しやすい
遺伝子の変異の影響の仕方が関与していると考えられている常染色体劣性遺伝性脊髄小脳変性症は小児期に発症するケースが多いと言われています。
- 劣性遺伝・・・2つある遺伝子の両方とも異常遺伝子でなければ発症はしない。
- 優性遺伝・・・片方は正常であっても、もう片方の遺伝子が異常であれば発症する。
劣性遺伝の場合は最初から正常な遺伝子がないので、その殆どが小児期に発症すると言われています。
脊髄小脳変性症における遺伝子変異の特徴とは?
脊髄小脳失調症3型、6型、歯状核赤核淡蒼球ルイ体萎縮症(DRPLA)では特に遺伝子によくみられるリピート(繰り返し配列)が異常な伸長があるという変異が特徴です。
3型、6型、DRPLAではCAG(アミノ酸の一種のグルタミン)の配列が通常よりも長く伸びます。
重症度は配列が長ければ長いほど高く、発症年齢は若くなります。
受精するときにこの配列が伸びるという特徴があるので、子どものほうが両親よりも重症度が高くなり、また両親よりも先に脊髄小脳変性症を発症することがあります。
脊髄小脳失調症31型の場合では、DNAを鋳型として合成され、タンパクの調整ををするRNA(リボ核酸)に相当する5塩基リピートに異常な延長と挿入がみられます。
このように、上記3つの病型は、すべてリピートによって起こる遺伝子異常といえます。